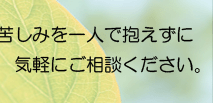|
|
和歌山市 泌尿器科・内科 北村泌尿器科内科クリニックのホームページへようこそ |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
||||
| >>症状と病気について | |||||
|
|
|||||
|
|
 |
 |
|||
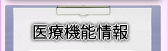 |
|||||
|
|
|
||||
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
1)前立腺肥大症
2)前立腺癌
3)慢性前立腺炎
4)膀胱炎(急性、慢性
5)過活動膀胱
6)不安定膀胱、神経性頻尿
7)間質性膀胱炎
8)神経因性膀胱
9)腎・尿管結石症
10)膀胱結石
11)膀胱腫瘍
12)腎盂・尿管腫瘍
13)腎腫瘍
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
泌尿器科の主な病気と、その診断のために必要な検査と治療について、簡単に説明します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1)前立腺肥大症 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
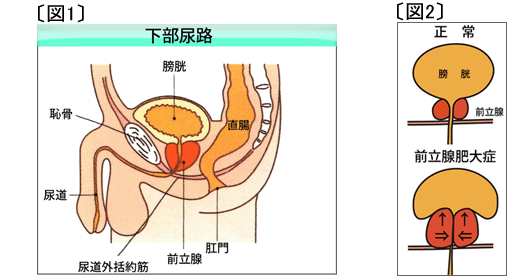 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
「前立腺」とは、〔図1〕のように、膀胱の下にあって尿道を取り囲む、男性にしかない臓器です。主な役割は、精液を造る事です。加齢と共に肥大した場合には、〔図2〕のように、尿道を圧迫して尿が出難くなったり、膀胱を突き上げて刺激するために、尿が近くなったりします。次第に、残尿(尿が出きらない)も発生します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2)前立腺癌 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
前立腺に発生する悪性腫瘍です。進行すれば、前立腺肥大症と同じような症状が発生しますが、初期には、全く症状がありません。その段階でも、血液中のPSA(前立腺特異抗原)を測定すれば、癌の有無の予測ができます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3)慢性前立腺炎 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
同じ前立腺の疾患でも、これは年齢に関係なく(若い男性にも高齢男性にも)発症します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4)膀胱炎(急性、慢性) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
大腸菌などの細菌が、尿道を経て膀胱へ入り込み、粘膜に炎症(腫れやただれ)を引き起こす病気です。その結果、頻尿(尿が近い)、排尿痛(尿を出す時や、出した後に尿道に痛みを感じる)、残尿感(尿を出したのに、スッキリしない)、等の症状が生じますが、人によって、状態によって、異なります。症状の無い人もいます。尿検査によって、診断される病気です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5)過活動膀胱 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
尿意切迫(尿をしたくなると我慢出来ない)を主な症状とする病気です。大抵は、頻尿(尿が近い)もあり、切迫性尿失禁(トイレへ行く迄に出てしまう)を伴う事もあります。女性に多く発症し、原因がよく分からない場合が多いようですが、全国に数百万人の患者さんがいる、と推測されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6)不安定膀胱、神経性頻尿 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
原因不明の頻尿(尿が近い)や残尿感(尿を出したのに、スッキリしない)が続く、または繰り返す状態には、様々の診断名が付けられます。それらの中には、膀胱炎に引き続いて起きている場合や、他の診断が見落とされている場合もあります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7)間質性膀胱炎 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
40~60歳代に女性に多く発症する、原因不明(アレルギーや、膠原病とも関係している場合があります)の膀胱の慢性炎症性疾患です。尿が溜まった時の膀胱痛、頻尿(尿が近い)、尿意切迫(尿をしたくなると我慢出来ない)等が主な症状です。過活動膀胱などよりも症状が重い場合が多く、膀胱痛が強かったり、頻尿が激しくて、日常生活が困難になる場合も、しばしば見られます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8)神経因性膀胱 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
膀胱の働きが(何らかの理由によって)鈍ったり、過剰になったりするために、尿が出難くなったり、近くなったり、漏れたり、残ったり(残尿)するようになる病気です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9)腎・尿管結石症 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
尿管結石症は、腎臓に発生した結石が、尿と共に尿管へ降りてきて途中で詰まるために、腎臓が自身の尿で腫れて、痛みが生じる病気です。多くの尿管結石は小さく、90%以上は、尿と共に尿道から排出されます(自然排石)。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10)膀胱結石 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
腎臓から尿管を下降してきた結石は、膀胱に入ると、大部分はそのまま尿と共に、尿道から体外へ出てしまいます。しかし、たまたま、または、尿道が狭くなっている場合に、膀胱に残ってしまって、膀胱結石になります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11)膀胱腫瘍 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
膀胱内に出来る「できもの」です。90%以上は癌ですが、進行しない限り、症状はほとんど有りません。痛みを伴わない血尿(赤い尿が出る、または検尿で、尿潜血や赤血球が認められる)が、ほとんど唯一の症状です。また、エコーやCTで、偶然発見される場合もよくあります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12)腎盂・尿管腫瘍 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
腎盂(腎臓内部の袋)や尿管に出来る「できもの」です。膀胱腫瘍と同様で、90%以上は癌ですが、進行しない限り症状はほとんど有りません。痛みを伴わない血尿(赤い尿が出る、または検尿で、尿潜血や赤血球が認められる)が主な症状ですが、尿管結石のように尿の流れを妨げて、腎臓が尿で腫れて痛みが生じる場合もあります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13)腎腫瘍 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
腎臓実質に発生する「できもの」です。多くは、腎細胞癌と呼ばれる癌です。膀胱腫瘍と同様に、進行しない限り、症状はほとんど有りません。痛みを伴わない血尿(赤い尿が出る、または検尿で、尿潜血や赤血球が認められる)が、ほとんど唯一の症状です。また、エコーやCTやMRIで、偶然発見される場合もよくあります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| >>前ページへ戻る >>このページのTOPへ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||